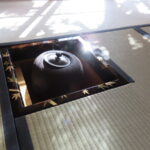昼顔科の花その一 小昼顔
雲の合間からのぞく空色のような
しっとり染まった青の
たった一輪の小昼顔の妖精です。
その二 浜昼顔
童女のほほえみを、空に託し
やや丸い葉をシッカリつなぎあって
昼顔科 その三 夜顔(よるがお)
しだいに 夜がせまり
真白い妖艶な夜顔の花が
たった一夜の思いを込め
葉音の囁きを聴きながら
ゆっくりと静かに、しずかにひらく
この夜顔は明治時代に渡来した花なので、源氏物語に登場する「夕顔」とは違います。
夕顔はウリ科で干瓢になる花です。夜顔は空が白けるときは本当に儚い姿になりますので
光源氏には合いそうな気がしますが?
「心あてに それかとぞ見る 白露の 光添えたる 夕顔の花」 紫式部
続きを読む
つゆ空に花咲かせてくれた紫陽花に惜別の思いを

さまざまな姿で楽しませてくれた紫陽花さんありがとう。
どうぞ、緑の葉の上でお休みください。
野花は心の花となりて、
とわに咲きつづけてくれます。
続きを読む
祇園祭でクライマックスの長刀鉾(halberd float)の巡行にお口に優しいレンコン粽(sweetened and jellied lotus root paste wrapped in bamboo leaves)

京の町は心が一番”あつい”鉾の巡行の日。
長刀鉾が先頭で稚児が誇らしげに。
この長刀は疫病の悪霊を取り除く力があるそうです。
This halberd is said to have power to exorcise the evil sprits
which cause epidemics.
この長刀鉾の香合にあやかりこの夏を切り抜けたいですね。
粽はひんやり喉に優しく、蓮根羊羹(れんこんようかん)が、包まれています。
なかなかの美味で、三昇堂小倉さんのです。
粽を載せているのは、檜の木による扇です。
祇園祭に活けられる檜扇のお花はここからきたと。
(この扇を教えてくださった方がおっしゃてました。)
祭りの後の静けさを
楚々としたペチュニアから感じます。
(しかし、今年から後祭りがあるそうですが・・・・・・・)
続きを読む
祇園祭近きて胸さわぎ、鉾のお菓子に姫檜扇(ひめひおうぎ)水仙(Astilbe thunbergii)と と鳥脚升麻(とりあししょうま)

蒸し暑い最中に、京都では一気に祇園祭のムードに染まっていきます。
一足お先に感じさせていただきます。
可愛らしい鉾の和菓子です。鶴屋吉信製 height=”240″ width=”320″>
height=”240″ width=”320″>
鵜籠の花入れに野趣あふれる、鳥脚升麻(とりあししょうま)に
姫檜扇水仙が祭りの歓びを
続きを読む
素敵な訪問者たち、オクラ(okra), 西瓜(watermelon) ,メロン(melon),とまと(tomato)と小さな籠の草花との語らい

無彩色の雨がふりつずく朝に
突然の訪問者たち
美しいオクラの姿と、色にうっとり
一人暮らしの我が身に寄り添った
西瓜とメロンのデザートまで
汗水流されての収穫物に、人の優しさまで
たっぷり籠にもられ、
雨の音も嬉しいメロデイーになりそうです
以前 天皇陛下が雑草という植物はないとおっしゃいました。
この草たちも名前があり、長いのは髪草(かもじくさ)といい
小さな紫の花のは松葉海ラン(まつばうんらん)
そして長いこと楽しませてくれた蔓桔梗さん
小さな籠の中で、しばらく休んでくださいね
ブランチに、フレンチトーストにパセリとりんごのジュースでいただこます。
箸置きにも一輪添えて
続きを読む
台風の無事に安堵して、真っ赤なフサスグリの実と(red currant) 真っ青な実のイシカワミ(Mile-a-minute-Weed)に水菓子にピンクの実とブルーベリーの実も加わってにぎやかに

まるで小さな宝石を散りばめたような
胸の中にしまっておきたいような
赤フサスグリの実
真白いターバンを巻いたトルコ桔梗が
広い水面のガラスの湖に
「大丈夫だよ」っと手を差し出した一艘の小舟
静かな波模様を描きながら
深いふかい藍色の実が待つ村に
こぎい出た初夏の午後

イシカワミは蔓性で小さな棘がありますが
本当に藍色した実が雨にぬれ輝いています。
日本ではまだ砂糖が入ってこない時代、お菓子は木の実や野菜、果物がそれに値するものでした。
それで水菓子と表現され、今でも祝儀袋に”水菓子”と。美しい日本語ですね。
今日は、実の形の 紫蘇のゼリーとブルーベリの実の共演です。
茶葉は中国から世界に広がったものですが、広東省の呼び方であった「チャ」は
シルクロード経由韓国はcha 日本は茶チャ、 sa サ モンゴル、トルコはchay チャイ
ギリシャは tsai チャイと発音され、福建省で呼ばれていた”テ”は海路で西洋諸国にまで伝わりました。
インドはtey テイ、オランダはthee テー イギリスはtea テイー ドイツはteeでテーと発音されたそうです。
今日の茶はドイツのteeです。
何世紀の歴史や経路をへて
このような美味の飲み物になった自然の恵みに
感謝していただきます。
続きを読む
台風予報にも爽やかにサンキライ(Smila china))の葉と紫陽花(Hydrangea)がアンテイークボトルに

美しい絹糸の額に、さんきらいの一葉と
葉脈だけになった草と。( 樹のようにみえます)
サンキライを漢字で現すと山帰来。別名サルトルイバラ。
枝に少し棘をもちつつも、ユニークなカーブを自慢気に。
油絵具のような葉も、楽しげに手をつないるようで。
花瓶はヨーロッパの古いワインのボトルではないかと思いますが?
今日の雨露のような鈍いひかりを放してます。
この葉を用いた和菓子もあり、
又便秘薬で有名な毒掃丸にも配分されてるそうで
いろいろ御世話になってます。
今日の雨の中にも薄青いあじさいがまだまだ主役です。
装飾花がてまりのようになったので「てまり咲き紫陽花」とか。
”TUBE”に”紫陽花”という歌があるそうですが、
どんなメロデイなのでしょうか?
”せせらぎ”というお店で、鍵善製のおかしとカフェオーレで
友人と雨宿りのテイータイムでした。
続きを読む
梶(かじ)の葉と天の川 The Milky Way

<
今日は七夕(しちせき)の節句です。
今はあちこちに笹飾りがみられ、日本の四季の嬉しい光景ですね。
古来中国の乞功奠(きっこうでん)に、日本古来の棚機津女(たなばたつめ)信仰が混ざり合った行事です。
平安時代はこの梶の葉に詞や歌を書き、江戸時代になって短冊に書いて笹に飾るようになったそうです。
「天の川と渡る船の一に思うことも書きつくるかな」後拾遺集より
「一を朗詠集のしをりかな」蕪村の句より
この梶の葉は、諏訪神社のご神紋であり、和紙の原料でもあります。
金平糖で天の川を描きました。今宵が雨でないように祈りながら、
近所の方にいただきました俵屋製のお煎餅です。
毎年、この時期になりますと神木のカジの葉に尊敬の念を抱き、かかせていただいてます。
本来は葉の裏に書くそうですが、(表の方が書きやすいので、)
続きを読む
蛍袋(Bellflower)とほたる(Firefly)

つゆ空にもわずかの陽のありがたさに、人も植物もうなずきあっています。
数種の野花、えのころ草の、黄花コスモス、白いほたる袋の花が今日の主役です。
外の世界では雨に打たれながらも健気(けなげ)にうつむいて咲いています。
きっと、蛍を恋しく待ち望んでいるのでしょう。
むかし、子供たちが蛍をいれ遊んでいる光景が偲ばれますね。
また、別名 提灯(ちょうちん)花というそうです。
なるほど、形が似てますね。昔は提灯のことを火垂るといったから。
ホタルの餌のカワニナは澄んだ川にいて、近年蛍が飛び交う光景が
ニュースで放映され嬉しいですね。
オスがメスを誘う時、光を連続5回ほどフラッシュ発光するそうで、
なんとロマンチックなしぐさでしょう。
ほんの数週間の命を燃やし、人間に感動を与えてくれる生き物に
儚い(はかな)余韻だけを毎年残ります。
まして、このような飴というかたちでお菓子のテーマにまでなり
心苦しいばかりです。
続きを読む
ミニひまわりとベビードーナツ

いよいよ今日から7月ですね。暦では半夏(はんげ)の季節で、
まだ梅雨の最中ですが、汗がにじむ一日でした。
ミニひまわりが夏の訪れのハミングをしているようです。
少し、カーブして踊っていらっしゃる葉はオオバコの仲間のヘラオオバコです。
子供の頃、二人で茎を挟み草相撲をした記憶がよみがえってきます。
今の子はこんな遊びはしないのでしょうか?
パンやさんに売っていたベビードーナツに、schwarzteeという紅茶です。
紅茶は100%発酵の茶葉ですので、熱湯で色をあざやかに。
今日は袋から出したばかりなので、香りも新鮮で美味しいです。
続きを読む